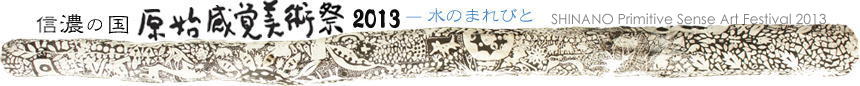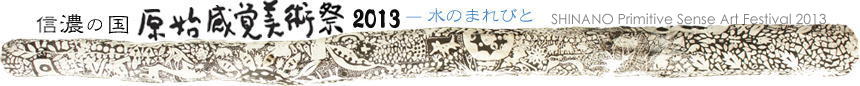|
 |
|
| 信濃の国 原始感覚美術祭2013 ―水のまれびと |
|
| 開催期間 2013年8月3日 [土] - 9月8日 [日] |
| 開催地 西丸震哉記念館、木崎湖畔、大町市街ほか |
|
| 主催 原始感覚美術祭実行委員会 |
| 共催 西丸震哉記念館、大町市教育委員会 |
| 実行委員長 神原三保子 |
| アートディレクター 杉原信幸 |
| コーディネーター 池田武司 |
|
| 平成25年度 長野県 地域発 元気づくり支援金事業 |
|
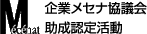 |
|
| 後援 |
|
| 長野県/大町市/長野県教育委員会/大町市観光協会/大町商工会議所 |
| 大町博物館連絡会/安曇野アートライン推進協議会/信濃毎日新聞 |
| 中日新聞社/abn長野朝日放送/朝日新聞長野総局/大糸タイムス社/市民タイムス |
|
| 協力 |
|
| 東京大学文化資源学研究室/慶應義塾大学アートセンター/JR東日本 |
| NPO松本クラフト推進協会/麻倉プロジェクト/創舎わちがい/塩の道ちょうじや |
| 薄井商店/海ノ口自治会/森自治会/稲尾自治会/古民家山本邸/大町文化財センター |
| 虹の家/北ヤマト園/海ノ口キャンプ場/Yショップニシ/アースデイ大町/千年の森 |
| NPOぐるったネットワーク大町/グリナ―ズビレッジ/おおまちラボ/あたらしや |
| 木崎湖キャンプ場/松葉屋旅館/社会福祉法人やまなみ会/NPO地域づくり工房 |
| サムサラ/大島健一/美麻小中学校/八坂小学校/井戸尻考古館/いーずら大町特産館 |
|
|
| 参加作家はこちら |
|
| 信濃の国 原始感覚美術祭2013について |
|
| 今年で4年目を迎える原始感覚美術祭は、縄文の文化の花開いた信濃の大地との結びつ |
| きを深め、名称を「信濃の国 原始感覚美術祭2013」と改め、開催されます。テーマは |
| 「水のまれびと」。アルプスの雪解け水を豊かに湛える木崎湖畔へ、古代のヒスイの路、 |
| 塩の道を辿って訪れる客人(マレビト)としてのアーティストが、この夏、新たな祭の |
| 渦を巻き起こします。 |
|
| マレビトの運んでくる新鮮な感性と、大地に住まう人の宿す原始的なものの気配が出会 |
| うことで、両者の邂逅によってしか生まれえない表現と文化を創造します。それは都市集 |
| 約型の文化ではなく、地方と呼ばれる大地の持っている地の声を、縄文人が豊かな生命の |
| の躍動として謳いあげた表現力として、大地こそが声を発している。地方と呼ばれる地の |
| 持つ力、地の方へ、地の方へと近づいていくことで、耳を澄まし、原初から受け継がれる |
| 根をもつ文化を共につくることから始めましょう。 |
|
| 都市空間によって規定された都市生活によって、生活とアートはまったくの別物として |
| 切り離され、生活者にとってアートは自分とは関係のないよくわからないものとして扱わ |
| れています。しかし、地方には生活の中から生まれる遊びの心の形としての表現が残って |
| います。そして縄文時代を見つめれば、常に表現は生活の中にあたりまえに存在していま |
| した。大震災と大津波、原発事故を経て、今、本当に新たな世界の在り方が求められてい |
| ます。アートや生活、科学や信仰、経済などさまざまに分けられ、切り離されてしまった |
| ものを、何一つおろそかにせず、繋ぎ直していくことで、生を回復していくこと。 |
|
| そこでは無農薬合鴨農法を行う農家の方と、稲を守ってくれた鴨の命を自らの手で奪い |
| 捌いた肉を感謝をもって食べることで、一度は失われた命が、再び体内に還ってくる。そ |
| の最も日常的な食という行為に含まれるかけがえのない生を繋いでいく営みは、ごくあた |
| りまえのことの中に、神秘が潜んでいることを教えてくれます。都市というばらばらにさ |
| れた身体性から、新たなアイデアを生み出すのではなく、自然と人とが共生関係を持ちえ |
| る場所から立ち上がる身体性によって、新たなビジョンを生み出していく。そのジャンル |
| を超えたさまざまな感性が集うことで、失われた身体性を回復します。自己表現や個とい |
| うものに閉ざされた都市の身体性を、解き放つ大いなる身体性によって開かれるビジョン |
| こそが、祭であり、新たなるライフ、命の身体性かもしれません。そこに集う人すべてが |
| 作りだす場自体が、開かれた身体である原始感覚美術祭へ。 |
|
| アートディレクター 杉原信幸 |